 |
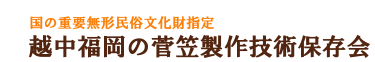 |
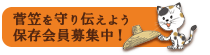 |
|||
 |
 |
 |
 |
 |
|
| 「 菅笠ができるまで 」 |
|||||
| 【その1】 スゲの栽培 植え付けの準備(9月上旬) | |||||
 |
 |
ツノ(イカリ)が良く出ているものを選び束ねます。 | |||
収穫したスゲの刈り株から、再生したスゲ苗を抜き取り、根元が太く新根の発生している良い苗を選びます。 苗を束ねて農業用水路などの流水につけ、植え付けまで保管します。 |
|||||
| 【その2】 スゲの栽培 植え付け(9月中旬~10月上旬) | |||||
 |
 |
「コロガシ」で植え付けの目印を付けます。 | |||
冬期の積雪の重みでスゲ苗が折れるのを防ぎ、新芽の成長を妨げないよう、苗の斜め植え(約45度)が手作業で行われています。 手作業のため、植え付けの目印として「コロガシ」と呼ばれる木製の枠を転がして枠を田に刻み、等間隔に植え付けします。 植え付けた苗は12月頃に枯れ、根元から新芽が出始めて積雪期を迎えます。 |
|||||
| 【その3】 スゲの栽培 間引き(ガス押し)(3月下旬~5月下旬) | |||||
 |
 |
ガス押し機の「ガス」とは、余分な細いスゲ草のこと。 間引きは、スゲを刈り取るまでに計3~5回行います。 |
|||
新芽(スゲの葉身)を3~4本ずつ残して、余分な芽をガス押し機で土の中に押し込み、間引きます。 間引きを行うことで、葉身幅が広く草丈の長い良好なスゲを育成することができます。 |
|||||
| 【その4】 スゲの栽培 刈り取り(7月中旬~8月中旬) | |||||
 |
 |
菅笠に使われるスゲ草は、カヤツリグサ目カヤツリグサ科スゲ属に属し、学名を「カサスゲ」といいます。 世界中で約2000種、日本には約300種のスゲ属の植物があります。 スゲは良く成長すると2メートル位まで伸びます。 |
|||
株を根元から握りこぶし一つ分(約10センチメートル)程残して刈り取ります。 スゲの葉縁にはノコギリの歯のようなギザギザの切込みがあるので、長袖を着て手袋を着用します。 |
|||||
| 【その5】 スゲの栽培 スゲ干し(7月下旬~9月) | |||||
  |
  |
スゲを干すには、日当たりがよく栽培面積の3倍以上の広い場所が必要。 夏は、福岡町内のいたるところでスゲ干しの風景を見ることができます。 |
|||
【バラ干し】 晴天の日に刈り取りしたスゲをバラして、丸一日天日干しを行います。 【扇干し】 スゲを葉先で結束し、扇状に広げ、晴天の日に4~5日程天日干しを行います。 表裏交互にして乾燥させると、初めは緑色だったスゲもだんだんと白色になっていきます。 |
|||||
| 【その6】 笠骨づくり(通年) | |||||
 |
  |
 竹を割って笠骨をつくります。 材料の竹はニガ竹、カラ竹、モウソウ竹。竹の性質に合わせ、ニガ竹は曲げやすいので中骨、カラ竹とモウソウ竹は丈夫なので外輪骨に使用します。 |
|||
| 【その7】 笠縫い(冬が最盛期) | |||||
    
|
1)スゲより |
スゲを選り分けます。 幅の広いスゲを「親スゲ」、中幅のスゲを「シカケスゲ」、一番細いスゲを「ヨリコ」と呼びます。 ・親スゲ/笠の表面に使用。 ・シカケスゲ/笠骨の内側にクモノ巣状に巻き付けるのに使用。 ・ヨリコ/笠骨の外輪骨などを結び付けるのに使用。 |
|||
2)仕掛け(又はハサンケともいう)  |
サシビラという道具(竹を割って板状にしたヘラ。20~30センチメートル程の長さ)で「シカケスゲ」の中央を刺し、上下に引き裂いて一本のスゲを二本にします。 笠骨に「シカケスゲ」を一本ずつクモの巣状に巻きつけます。  |
||||
3)ノズケ  |
笠骨の外輪竹と、小骨といわれる竹ヒゴの間に「親スゲ」を入れ、糸で止めます。  |
||||
4)スゲコキ  |
コキベラ(コクベラ)を使って、ノズケをしたスゲの表裏をこすって光沢を出し、柔らかくします。 |
||||
5)笠縫い   |
10センチメートル程ある長い笠針に黄色い糸を通し、一目一目外周から中心部へと渦巻状に縫っていきます。   縫い終わったスゲの端を編みこむようにして結びます。この作業を頭止めといいます。 |
||||